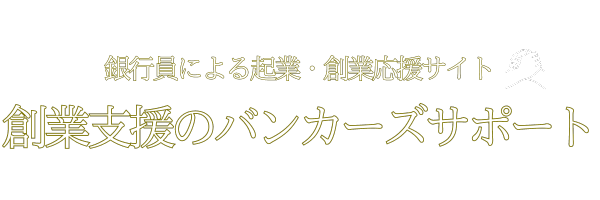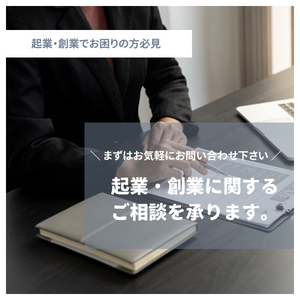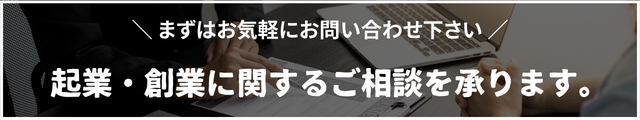創業を成功させるためには、適切な資金調達が欠かせません。しかし、資金調達方法には多種多様な選択肢があり、どの方法が最も効果的で安全なのか迷うこともあるでしょう。この記事では、開業資金の調達方法や政府の支援制度について詳しく解説していきます。自分に合った方法を総合的に把握し、スムーズな事業立ち上げを目指しましょう。
1. 開業資金の調達方法
開業するためには、適切な開業資金を調達する必要があります。起業や開業時の資金調達方法は様々です。以下にいくつかの方法を紹介します。
1.1 出資
出資は、対象の団体や事業にお金や財産を提供する方法です。主な出資方法は以下の通りです。
- 自己資金: 起業家自身の個人資産を資本として使う方法です。自身の経営権を保つことができるメリットがありますが、利用できる資金には限りがあります。
- 社員持株会: 社員が設立した会社の資本金を出資する方法です。社員の参加意欲を高めることができますが、運営には注意が必要です。
- 他企業からの出資受け入れ: 株式を他企業に譲渡して出資を受ける方法です。出資元企業との交渉が重要です。
- ベンチャーキャピタル(VC): ベンチャーキャピタルから資金を受け入れる方法です。経営アドバイスやネットワークの提供が期待できます。
- エンジェル投資家: 個人の投資家から資金を受ける方法です。返済条件が緩和されるなどのメリットがあります。
- クラウドファンディング: インターネットを通じて意欲的なプロジェクトに資金を提供する方法です。リスクが低く、同時にテストマーケティングの場としても活用できます。
※出資に関する具体的なメリットやデメリットについては、参考文献『1』をご覧ください。
1.2 借入(デッドファイナンス)
借入は、金融機関からの融資などを利用して資金を調達する方法です。以下に代表的な借入方法を紹介します。
- 銀行の融資: 銀行からお金を借りる方法です。返済計画や担保の用意が必要です。
- 手形割引: 手形を割引して現金化する方法です。手形の信用度によって借入までの手続きが変わります。
1.3 資産を現金化(アセットファイナンス)
資産を現金化する方法もあります。以下に代表的な方法を紹介します。
- ファクタリング: 売掛金をキャッシュ化する方法です。売掛金の回収を先行させ、資金を調達します。
- リースバック: 所有する物件を売却し、同時にリース契約を結ぶ方法です。現金を得ることができます。
1.4 補助金・助成金
補助金や助成金を利用する方法もあります。創業補助金や再就職手当などが代表的です。詳細な情報や申請方法については、自治体や関連機関のウェブサイトを確認してください。
これらの資金調達方法は、事業規模や事業内容に合わせて適切な方法を選ぶことが重要です。自己資金、借入、出資などの方法の利点やデメリットを比較し、最適な資金調達方法を選択しましょう。
2. 日本政策金融公庫の新創業融資制度
日本政策金融公庫は、新しい起業やまだ始まったばかりの事業を支援するために、6つの融資制度を提供しています。その中でも「新創業融資制度」は、特に注目されています。
2-1. 新創業融資制度の特徴
新創業融資制度は、新しく起業を考えている人や起業してから間もない人向けの融資制度です。この制度では、通常は担保や保証人が不要です。そのため、起業を考えている人々の間で高い支持を集めています。
ただし、新創業融資制度は単体で申し込むことはできません。他の融資制度と組み合わせて利用することで、担保や保証人なしで融資を受けることができます。イメージとしては、オプションのような使い方ができる制度です。
2-2. 新創業融資制度の対象者と融資条件
新創業融資制度を利用するための対象者は、以下の要件を満たす必要があります: - 新しく起業する人、または事業開始後の税務申告(確定申告)を1期終えていない人 - 創業資金の10分の1以上の自己資金が用意できること
融資の使途は主に設備投資や運転資金であり、融資限度額は3,000万円(運転資金は1,500万円)です。返済期間は他の融資制度に準じます。金利は基準金利であり、借入期間が7年以上になると利率が上昇する場合があります。
新創業融資制度は他の融資制度との組み合わせが一般的です。特に、「新規開業資金」と組み合わせると低金利になるため、該当する場合にはおすすめです。また、「女性、若者/シニア起業家支援資金」や「再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)」の要件を満たしている場合も、これらの融資制度と組み合わせることで低金利利率を利用することができます。
以上が、「新創業融資制度」の概要と特徴です。次のセクションでは、「新規開業資金」との比較について詳しく解説します。
3. 新規開業資金概要
新規開業資金は、事業を始める人やお店を開く人が利用できる制度です。以下に、新規開業資金の主な特徴をまとめました。
利用可能な方
- 事業をこれから始める、もしくは事業開始後おおむね7年以内の方
資金の使い道
- 事業の開始、継続に必要な設備資金および運転資金
融資限度額
- 7,200万円(うち4,800万円は運転資金)
返済期間
- 設備資金:最長20年(うち据置期間は最長2年)
- 運転資金:最長7年(うち据置期間は最長2年)
利率
- 基準利率(1.03%~2.95%)が適用されますが、特定の条件を満たす場合には特別利率を受けることができます。
- 特別利率A(0.63%~2.55%)は、地域おこし協力隊としての活動地域で事業を始める、Uターンをして地方で事業を始める、認定特定創業支援等事業や外国人起業活動促進事業における特定外国人起業家として事業を始める場合に適用されます。
- 特別利率B(0.38%~2.30%)は、35歳未満または55歳以上の女性の方、独立行政法人中小企業基盤整備機構から出資を受けた場合、新たな技術やノウハウを導入する場合に適用されます。
- 特別利率C(0.30~2.05%)は、地方創生推進交付金を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める場合に適用されます。
担保、保証人
- 融資ご希望の方によっては担保や保証人の提供が必要となる場合があります。具体的な要件については、相談してください。
新規開業資金は、事業をスタートさせるために必要な設備購入や運転資金を調達するための制度です。適切な事業計画を策定し、審査に合格することが条件となります。起業に必要な資金計画を立てる際は、具体的な費用や必要な資金の内訳を明確に把握することが重要です。
4. 新創業融資制度の特徴と新規開業資金との比較
新創業融資制度と新規開業資金は、日本政策金融公庫が提供している融資制度ですが、一定の違いが存在します。このセクションでは、新創業融資制度と新規開業資金の特徴と比較を見ていきましょう。
4.1 新創業融資制度の特徴
新創業融資制度は、新たに事業を始める方や事業を始めてから2期終えていない方を対象としています。この制度は、他の融資制度と組み合わせて利用することで、担保と保証人なしで融資を受けることができます。
特徴: - 対象者は新たに事業を始める方や事業を始めてから2期終えていない方。 - 原則的に担保と保証人は不要。 - 融資限度額は最大で3,000万円(運転資金は1,500万円)。 - 返済期間は他の融資制度に準じ、借入期間が長くなるほど利率が上昇する場合がある。 - 利率は基準金利(令和5年2月現在2.33〜3.45%)が適用され、一定の要件を満たす場合は特別利率が適用されることもある。
4.2 新規開業資金との比較
新規開業資金と新創業融資制度の主な違いを以下にまとめます。
- 制度の対象: - 新創業融資制度:新たに事業を始める方、または事業を始めてから税務申告を2期終えていない方。 - 新規開業資金:新たに事業を始める方、または事業を始めてからおおむね7年以下の方。
- 融資限度額: - 新創業融資制度:最大で3,000万円(運転資金は1,500万円)。 - 新規開業資金:最大で7,200万円(運転資金は4,800万円)。
- 担保・保証人: - 新創業融資制度:原則的に担保と保証人は不要。 - 新規開業資金:原則的に担保と保証人は必要。
- 返済期間: - 新創業融資制度:他の融資制度と同様の返済期間が適用される。 - 新規開業資金:設備資金は最長で20年以内、運転資金は最長で7年以内の返済期間がある。
- 利率: - 新創業融資制度:基準金利(令和5年2月現在2.33〜3.45%)が適用される。 - 新規開業資金:基準金利(令和5年2月現在2.03〜3.15%)が適用される。
- 優遇措置: - 新創業融資制度:法人が借入れをした場合には、代表者個人には責任が及ばない。また、代表者が連帯保証人となる場合には、利率が0.1%低減される。 - 新規開業資金:技術やノウハウに新規性が認められる場合など、一定の要件を満たす場合は金利が優遇される。
新創業融資制度と新規開業資金は、日本政策金融公庫が提供している融資制度ですが、利用条件や融資限度額、返済期間、利率などに一定の違いがあります。新創業融資制度は他の融資制度と組み合わせて利用することで、担保と保証人なしで融資を受けることができます。一方、新規開業資金は新たに事業を始める方や少ない経験を持つ方を対象としており、一定の要件を満たす場合は金利が優遇されることもあります。適切な融資制度を選ぶためには、自身の起業の状況やニーズに合った制度を選択することが重要です。
5. 融資を検討する際のポイント
融資を検討する際には、以下のポイントに留意しましょう。
1. 借入金額を返済できる計画性が重要
融資を受ける際には、返済計画を立てる必要があります。借入金額には利息も含まれますので、返済義務を適切に果たすためには、無理のない計画性が求められます。売上だけでなく、経費や税金などの費用も考慮に入れ、返済計画を立案しましょう。
2. 補助金や助成金の活用も検討する
融資だけでなく、返済義務のない補助金や助成金の利用も視野に入れましょう。補助金は公募期間や採択件数に制約があるため、受給できる保証はありません。助成金は通年で申請が可能ですが、特定の要件を満たす必要があります。融資と併せて、補助金や助成金の活用も考慮することで、より安定した資金調達が可能となります。
融資を検討する際のポイントは以上です。利息の計画性に加えて、補助金や助成金の活用も考慮しましょう。ただし、返済能力や計画についての説明は必要です。順調な事業計画と借入計画を立て、適切な金融制度を選択しましょう。
まとめ
事業を始めるためには、適切な事業資金の調達が必要です。様々な方法がありますが、自己資金、借入、出資などの方法を比較し、最適な資金調達方法を選ぶことが重要です。また、日本政策金融公庫の新創業融資制度や新規開業資金制度を利用することも一つの手段です。融資を検討する際には、返済計画の立案や補助金・助成金の活用も検討しましょう。順調な事業計画と適切な金融制度の選択により、安定した資金調達を実現しましょう。
よくある質問
Q1. 融資を受ける際に必要な申請書類は何ですか?
申請書類は申込金融機関によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要とされます:
- 法人の場合:会社設立登記簿謄本、役員の戸籍謄本、事業計画書、財務諸表など
- 個人事業主の場合:住民票の写し、納税証明書、事業計画書、財務諸表など
具体的な申請書類については、申込金融機関のウェブサイトや担当窓口で確認してください。
Q2. 融資を受けるために必要な返済能力とはどういう意味ですか?
返済能力とは、借入金や利息を返済する能力のことを指します。融資を受ける際には、返済能力を示すために収入や資産の状況などを提出する必要があります。金融機関は返済能力を評価し、借入の承認を判断します。
Q3. 融資を受ける場合に担保や保証人は必要ですか?
融資を受ける場合、金融機関によって異なりますが、一般的には担保や保証人の提供が求められることがあります。担保は財産などを差し出して借入金の担保とすることで、返済能力を補完する役割があります。保証人は借入の返済を補完するために債務者の責任を負う存在です。
Q4. 助成金や補助金の活用方法について教えてください。
助成金や補助金は、起業や事業展開を支援するために自治体や関連機関から支給される資金です。具体的な活用方法は助成金や補助金の公募要項を確認し、必要な申請書類や手続きを行うことです。それぞれの助成金や補助金には様々な条件や制約があるため、詳細な情報は関係機関のウェブサイトや窓口で確認してください。